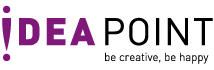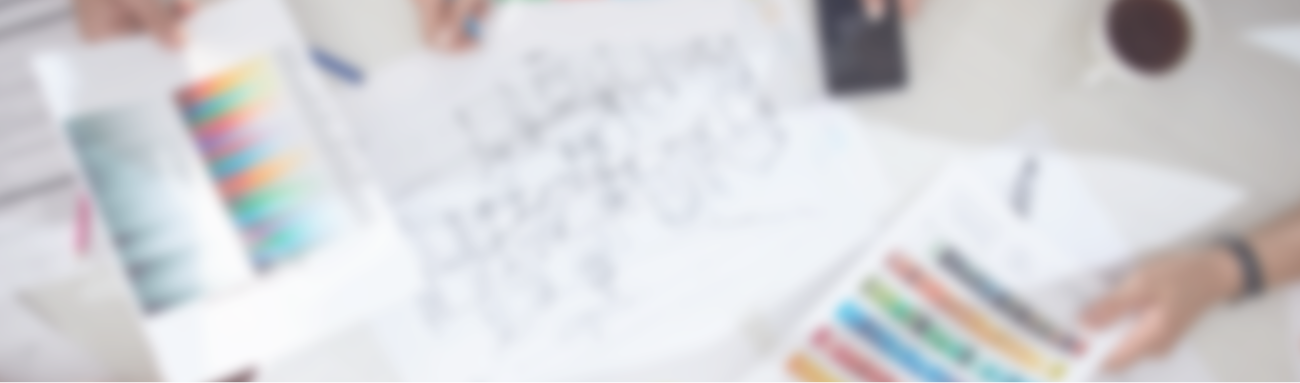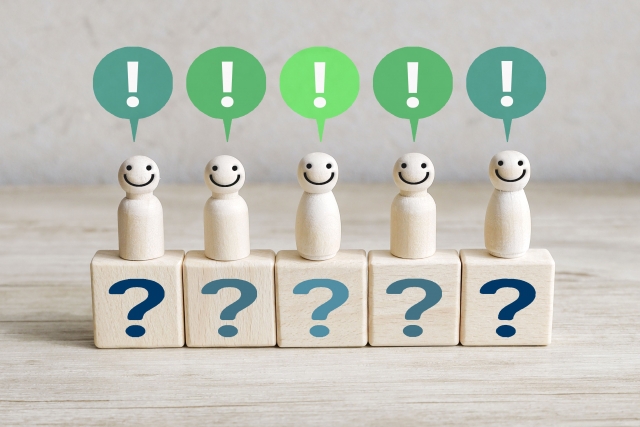
※:このブログは岩田徹(人間)が書いています
アイディアポイント岩田です。9月になって急に涼しくなりましたね。いかがお過ごしでしょうか。当社は9月から繁忙期ということで、しっかり準備して毎日忙しく過ごしています。と言いながら、まだまだ後半戦は私のスケジュールに空きがありますので、お仕事の相談、ドシドシ、ご連絡ください!!
さて、今回のテーマは、『バズワード』です。様々な勉強会で『バズワードみたいになってしまっている』という枕詞を聞くことが多く、「バズワードは意外と無視できない」と思ったことがきっかけです。今回は、私たちビジネスパーソンは、『バズワード』について、どのような姿勢で取り組めばよいのかまとめていきたいと思います(この内容は、次回、人事の勉強会で話す内容の一部です)。
『バズワード』は面倒くさいけど、どうしたらよいかな?効率よい調べ方はないかな?と思った方は参考にしてください。今回は、私が実践していることをまとめています。
ところで、バズワードとは何か?
議論のスタートは言葉の定義です。ChatGPTに聞いてみましょう!バズワードとは何ですか?
—
「バズワード(buzzword)」とは、一見すると新しくて格好良く、注目を集めやすい流行的な言葉を指します。よく使われるのはビジネスやITの分野で、専門性があるように見えて実は曖昧だったり、具体的な内容が伴っていなかったりする場合が多いです。例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)、シナジー、サステナビリティ、パラダイムシフトといった言葉は「バズワード」と呼ばれることがあります。要するに、「流行っているけど、人によって解釈が違ったり、実態がはっきりしないキャッチーな言葉」 という意味ですね。ビジネスの場では、耳障りはよいけれど中身が伴っていない使い方をすると「バズワードを並べているだけだ」と揶揄されることもあります。
とのことでした。「はやっていて」、「なんとなくわかるような気がするけど」、「なんだかよくわからない」言葉のことのようですね。たくさんありますね。
ビジネスパーソンにとって、『バズワード』は、なかなか悩ましい存在
意外と多くのビジネスパーソンにとっては、『バズワード』は、悩ましい存在なのではないかと思います。なぜならば…
- なんとなくみんな知っている風で、よく使われるので、「知らないといけない」キーワードではある
- が、その言葉の概念があやふやだったり、言葉が定義されていないことが多い
- なのに、なんとなくみんなが使っているので、会話に出てくる
- 今更、「それどういう意味ですか」と聞けない
からです。『DX(デジタルトランスフォーメーション)』がわかりやすい例ではないでしょうか。スルー出来ないのがなかなかやっかいなところですね。
実際、商談の冒頭で、『弊社ではDXが課題で~~』と話を切り出した人が、打ち合わせの後半で、こちらがDXという言葉を使ったところ、『DXって何ですか』と聞いてくるケースも多く見受けられます。「いやいや、逆に、さっき、どんな意味で使ってたんだよ!」とは言いませんが、よくあるケースです。難しいものですね。
とは言え、よく流通している言葉なので、避けたり、無視したりするわけにもいきません。いちいち、定義をするのもスマートではありません。私たち、ビジネスパーソンはこの『バズワード』に対して、どのように取り組むべきなのでしょうか。それが今回のテーマです。
『バズワード』攻略のゴールは、「普通の人より少しだけ詳しくなる」、「持論を形成する」の2つ
バズワードについては専門家でない限り、ある程度の情報を理解して、正確にコミュニケーションできれば十分です。あまり、ハードルをあげずに、少し調べて、ノリや雰囲気で話すよりも「もう少し突っ込んだ」議論ができるところをゴールにしましょう。
『DX(デジタルトランスフォーメーション)』の例で言えば、「おぉ、DXね。DXだよね。DX大事だよね。やっぱりDXしないとね」から一歩踏み込んで、『自分としては、DXは~~だと理解しているけどね。デジタル化とは何か、トランスフォーメーションは何か議論しましょう』と一言添えられるくらいで十分です。そもそも、合意された定義があるわけではないので、自分なりに理解しておくことが重要です。
そのために、最低限の知識だけ調べておくというのが基本姿勢です。最低限の知識をどうやって身につけるのかが次のテーマです。
私がやっている『バズワード』を理解する4つのステップ – 当たり前なことほどやっておくと差がつきます
ここでは、私が必ずやっている『あるテーマ、キーワード』を理解するときにしている4つのステップを紹介します。今度、人事の皆さんに話す機会があるので、ここでは、『越境学習』、『エンゲージメント』、『HRBP』などを具体例に考えていきましょう。
注1:『越境学習』、『エンゲージメント』、『HRBP』が「フワッとした概念である」ということではなく、概念としてはきちんとしているのですが、流行っていて、多くの人が定義せずにノリで使っているということです。あしからず。
STEP1 : 最初に言葉の定義を確認する
最初は難しくないところからスタートしましょう。辞書でも検索でもAIでもよいので言葉の定義を調べましょう。意外と調べていない人が多いようです。できれば、自分なりに説明できるとよいでしょう。最初は↓くらいシンプルなところからスタートするとよいでしょう。
- 越境学習 : 越境して、学習すること
- エンゲージメント : 約束や契約
- HR BP : HR分野(人事分野)のビジネスパートナー(ビジネスを一緒に考えてくれる人、支援してくれる人)
いかがでしょうか?当たり前、簡単に見えるかもしれないが、意外とこの定義をきちんと押さえておくことが大事です。特に、カタカナはきちんと考え方を押さえていないと、ルー大柴みたいと影で悪口を言われかねないので注意しましょう(ちなみに、私はルー大柴は大好きです。一周回っておもしろいです。みなさんも一度、復習することをお勧めします)。
STEP2 : なぜ、いま、それがバズっているのか、その理由と経緯を理解する
次は、「ところで、なぜ、いま、それが注目されているのか」、「どういった経緯で注目されているのか」を考えてみます。ここは、一度、自分でシンプルに考えてみて、その上で、調べたり、AIに聞いてみるのが効率がよいでしょう。ここでは、『越境学習』を例に考えてみましょう。まずは、自分で考えてみましょう。
なぜ、いま、越境学習が注目されるのか?
→ 越境しないと学べないことが大事になっているのに、多くの人が越境していないから
→ 「新しいこと」、「挑戦すること」が求められているので、既存の仕組みでは「外に出る」仕組みがないから
→ これまでの「効率化」、「カイゼン」を中心にビジネスを伸ばすことがそろそろ難しいから
こんな風に考えてみるとなぜ、いま、それがバズっているのかわかるようになるはずです。その上で、ネットを調べたり、AIに聞いたり、記事を読んでみると大筋は理解できるでしょう。
再度、ChatGPTの登場です。なぜ、いま、このタイミングで越境学習が注目されているのですか?簡潔に教えてください。
>越境学習がいま注目されているのは、以下の背景が重なっているからです。
>変化の激しい時代
>技術革新や市場環境の変化が速く、1つの専門分野の知識だけでは課題解決が難しくなっている。
>イノベーションの必要性
>異なる業界や立場の知見を組み合わせることで、新しい発想や価値創出が求められている。
>働き方の多様化
>副業・リモート・越境的キャリアが広がり、社外の学びやつながりが自然に取り入れやすくなった。
>つまり「自社内だけでは学べない視点やネットワークが、これからの成長に不可欠」になったため、注目されているのです。
STEP3 : 似た言葉 / 概念、反対の言葉と比較して理解する
ここまでくれば、大体の意味は理解できていると思うので、もう一歩です。多くの新しい概念は、既存の概念のアンチテーゼあるいはそれでは説明できないものを説明するために生まれています。似たような言葉や対になる概念とどう違うのか理解することで、よりはっきりとその輪郭を理解することができます。例えば…
- 越境学習 : 社内研修、異業種交流研修、留学、留職、インターン など
- エンゲージメント : コミットメント、満足度、幸福度 など
- HR BP : 人事部、事業部人事、コンサルタント、メンバー など
みなさんは、これらの言葉との違いを説明できるでしょうか。中には、「同じだよ」と言う人もいますが、「絶対に違います」。100%同じ概念であれば、違う言葉が2つ存在することはありません。
『大体同じだよね』と思う人も注意が必要です。「言葉の解像度」は「思考の解像度」ですので、面倒に感じるかもしれませんが、自分なりに言葉にできるようにしてみてください。
意外と大変かもしれませんが、それほど難しく考える必要はありません。AIに聞いてみるとわかりやすく回答してくれます。
STEP4 : ここまでくればあとは簡単。記事を読みながら用語の「使い方」に慣れる
STEP3までできたら言葉の使い方に慣れるだけです。ネットで検索して、5-10程度、上位の記事を読めば使い方が理解できます。
越境学習を例に取ると… 「シニアが越境学習をする」、「地方に越境学習をする」、「ベンチャーに越境学習をする」、「これからのリーダーには越境学習が必要だ」など、どんな文脈で何が語られるのか理解できます。その中で、リーダーシップ、リスキリング、地方創生、新規事業創出など、異なるテーマも出てくるので、それらを読みながら、どんな使われ方をするのか慣れてきます。
ここまできたら、みなさんは、「他の人よりも少し詳しい」し、「私は、このキーワードについて、こう考える」と話せるくらいにはなると思います。
大体、ここまで25分くらいで終わらせるのが一つの目安です(私はポモドーロテクニックを採用しているので、ちょうどきりがよいのでそうなっています。個人的には集中して一気にやってしまうのが好きなので)。慣れてしまえば、それほど大変ではないので、これくらいやれるとよいのではないでしょうか。
ここから先は実践のみ - 外に出て人に会い、議論しよう
4つのSTEPを終えたら、あとは、実践のみ!です。一度、調べたみなさんであれば、素朴な疑問や他の人と議論したいこともたくさん出てくるでしょう。
実は、多くの人が「いまさら、聞けないけど、本当はこれ、どういう意味なんだろう」と思っています(多分)。
既に考えて、調べたみなさんなら、勇気を持って言えるはずです、「あらためて、〇〇って、どういう意味なのでしょうか」。ここを議論のきっかけにして周囲がどう考えているのか、具体的にどういう意味で使っているのか、なぜ、いま、それが必要なのか具体的に話しあってみてください。一度、議論したら、別の場所でその内容を活用していくと雪だるま式に議論の内容が溜まっていきます。ということで、これで、『バズワード』に困ることはもうありません。
ということで、今回は、『バズワード』と呼ばれるよくわらないんだけど無視できない言葉にどう向き合うのか書きました。みなさんは、「やっぱり面倒くさいな」と思いましたか?「意外とやれそうだな」と思いましたか?新しい概念は正解を教えてくれる人はほとんどいないので、人と議論しながら自分なりに理解するのが近道です。お仕事で「流行の概念」を理解しなくてはいけない人は、ぜひ、参考にしてみてください!
本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
株式会社アイディアポイント
代表取締役社長
岩田 徹