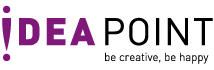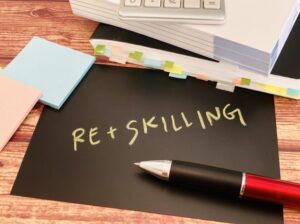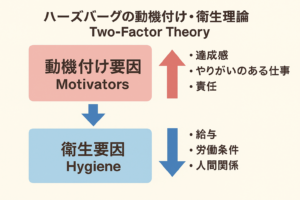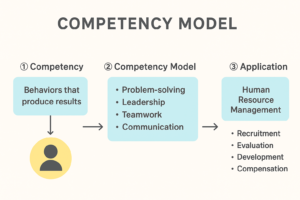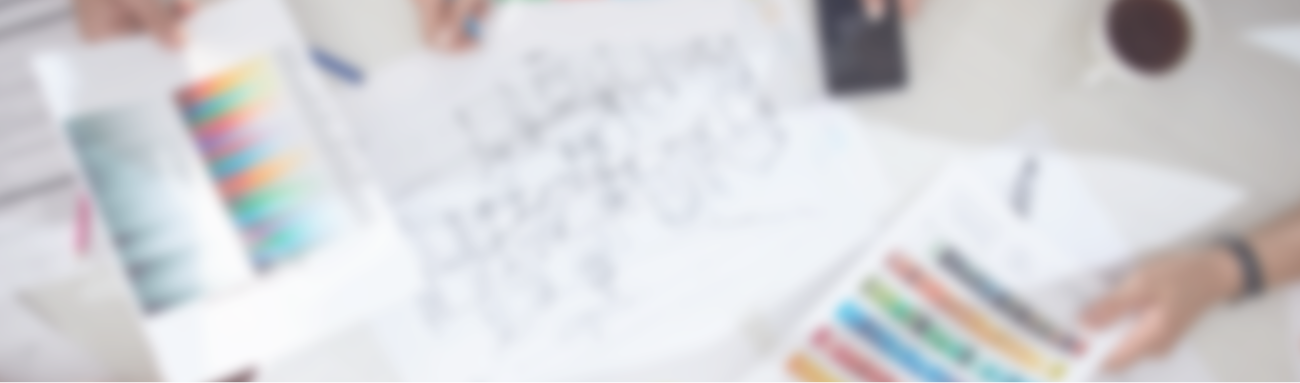日々の業務でよく使われるものの、その定義や基本的な考え方や論点について、「意外と知らない…」、「なんとなく知っているものの、実は理解があやふやなんだよなぁ」ということは実は言えないだけでよくあることなのではないでしょうか。
今回は、人事の分野でよく聞くキーワードとして、「サクセッションプラン」を取り上げて解説していきます。
1.サクセッションプランとは何か
1-1 サクセッションプランの定義
「サクセッションプラン(Succession Plan)」とは、企業や組織において重要なポジションを担う人材が退職・異動・不測の事態などで不在になったときに備え、その後任者を計画的に育成・選定しておく仕組みを指します。日本語では「後継者育成計画」と呼ばれます。
単に「次の社長を決める」という狭い意味ではなく、経営層からミドルマネジメント、現場のキーパーソンまで、組織の継続性を確保するための戦略的な人材マネジメント手法です。
組織は人によって動きます。優秀なリーダーが突然いなくなると、業績だけでなく、社員の士気や顧客との信頼関係にも大きな影響が出ます。サクセッションプランは、そうした「人のリスク」を最小化し、持続的な成長を支える仕組みと言えるのです。

1-2 なぜ今、サクセッションプランが重要なのか
近年、日本企業でもサクセッションプランが注目されています。その背景には、大きく3つの理由があります。
第一に、経営者や幹部層の高齢化です。特に中小企業では、後継者不在が深刻な問題となり、事業承継が滞るケースが増えています。
第二に、ビジネス環境の変化です。市場や技術の変化が速く、リーダーには変革対応力が求められるようになりました。優れたリーダーをタイムリーに育てることが、競争力の鍵になっています。
第三に、多様化する働き方や価値観です。終身雇用が崩れ、優秀な人材ほど転職や独立を選ぶ時代。だからこそ、社内でのキャリアパスを明確にし、成長を支援する仕組みとしてのサクセッションプランが重要なのです。
2.実際の企業に見るサクセッションプランの実践
2-1 P&Gの「リーダー育成文化」
グローバル企業の中でも、サクセッションプランの成功例としてよく挙げられるのがP&G(プロクター・アンド・ギャンブル)です。
P&Gは「リーダーを外から採用するのではなく、自社で育てる」という方針を徹底しています。新入社員の時点からリーダー候補としての成長を期待し、段階的にマネジメント経験を積ませる仕組みを整えています。
例えば、若手でも早い段階からプロジェクトリーダーを任せ、失敗から学ぶ文化を支援します。また、上司は「次の自分の後継者を育てること」も評価項目に含まれており、組織全体が後継者育成を意識して動いています。
その結果、P&G出身者は他社でも経営幹部として活躍しており、「リーダーの学校」と呼ばれるほどです。
2-2 トヨタ自動車の「チーム経営による継承」
日本企業の例としては、トヨタ自動車のサクセッションプランが参考になります。トヨタは「個人ではなくチームによる経営継承」を重視してきました。
例えば、豊田章男前社長から佐藤恒治社長へのバトンタッチでは、単なる交代ではなく、「トヨタの哲学や判断軸をどう共有し、次世代に渡すか」が中心テーマでした。
経営層は定期的に経営課題をチームで議論し、意思決定プロセスそのものを共有することで、誰か1人が抜けても組織が止まらない体制を整えています。
このように、トヨタは「個人のカリスマ」ではなく「組織の知」を継承する仕組みを築いており、長期的な競争力の源泉となっています。
2-3 スターバックスの「創業者からのバトン」
スターバックスも、サクセッションプランの好例です。創業者ハワード・シュルツは2000年にCEOを退任しましたが、後継者がうまく機能せず、再びCEOに復帰した経験があります。この失敗を踏まえ、次の後継者選びでは長期的な視点で育成を行いました。
2017年、ケビン・ジョンソンがCEOに就任した際には、数年間にわたる計画的な引き継ぎが行われました。ジョンソンはシュルツと密に連携しながら、スターバックスのブランド哲学を学び、経営判断の基準を共有していきました。
その結果、スムーズな世代交代が実現し、スターバックスは世界規模での成長を維持することができました。
3.サクセッションプランから得られる示唆と実践のポイント
3-1 サクセッションプランは「人の戦略」である
サクセッションプランの本質は「人を中心にした経営戦略」にあります。単に人材の穴埋めをする仕組みではなく、「誰をどう育て、どんな未来をつくるか」という企業の意思を示すものです。
そのため、経営陣が主体的に関与し、組織のビジョンや文化と結びつけて設計することが大切です。
3-2 早期発見・計画的育成の重要性
後継者候補は、突発的に選ぶものではありません。日常の業務の中で、将来のリーダーになり得る人材を早期に発見し、段階的に育成することが求められます。
評価制度や人事データの活用により、潜在能力の高い人材を見極め、育成プログラムやメンター制度を組み合わせて成長を支援する仕組みが有効です。
3-3 透明性と公平性の確保
サクセッションプランが機能するためには、「なぜその人が選ばれたのか」「どんな基準で評価されているのか」が組織内で理解される必要があります。
選抜プロセスが不透明だと、社員の不信感を招き、逆にモチベーションを下げてしまうこともあります。
評価指標を明確にし、オープンな対話を通じて納得感を高めることが、健全な後継者育成の鍵となります。
3-4 失敗を許容する文化の育成
リーダーを育てる過程では、失敗を恐れない文化が欠かせません。新しい挑戦の中で成長する機会を与え、結果だけでなくプロセスを評価する風土をつくることが重要です。
P&Gのように「次のリーダーを育てること」を上司の責任として組み込むことは、サクセッションプランを組織文化として根づかせる有効な方法です。
4.まとめ ― 組織を未来へつなぐバトン
サクセッションプランは、単なる人事の仕組みではなく、組織の未来を設計する経営戦略です。
企業がどんなに優れた技術や商品を持っていても、それを動かすのは「人」です。リーダーが次々と育ち、自然にバトンが渡される組織こそ、真に強い組織といえます。
そのためには、
- 経営層が明確なビジョンを持ち、
- 次世代を見据えた育成を計画的に進め、
- 失敗を恐れず挑戦できる文化を築くこと。
これらが揃ったとき、サクセッションプランは単なる制度ではなく、「未来をつくる仕組み」として機能します。
企業も個人も、「誰かの次」を考えることが、持続可能な成長への第一歩なのです。
今回は、人事の分野でよく聞くキーワードとして、「サクセッションプラン」を取り上げて解説しました。正しい活用は正しい理解から!みなさまの業務に活用いただければ幸いです。また、「実はこんな理論、コンセプトも解説してほしいんだよね」というものがありましたら、弊社営業までお問い合わせください。
本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
株式会社アイディアポイント
管理本部
高橋佑季