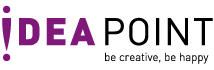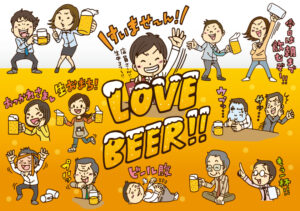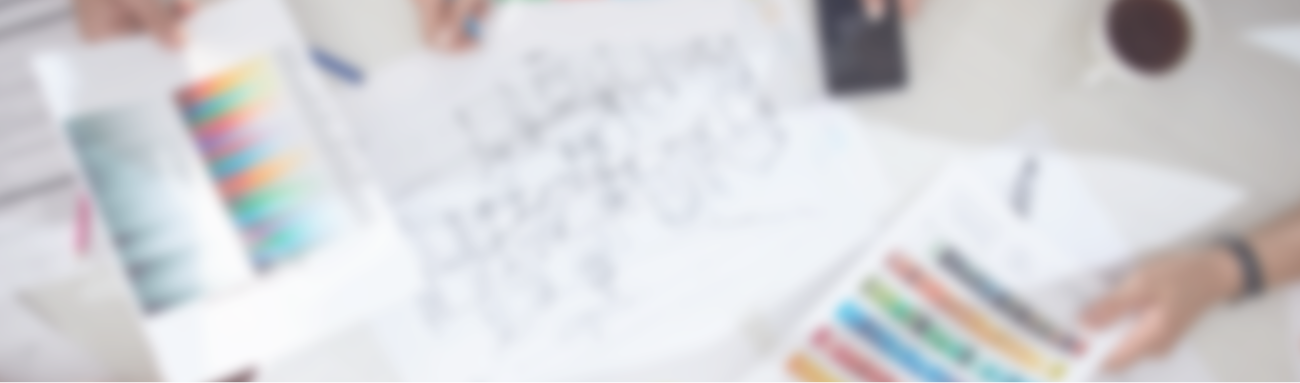アイディアポイント岩田です。年末年始、いかがお過ごしでしょうか。私たちの会社では年末年始に「報告会」、「発表会」が多くセットされています。私は各社でアドバイスするわけですが(もちろん、会社ごとに頭を絞ってお話するわけですが)、今年は、『持論 / 自論 x 議論』というキーワードで話すことが多いので、この点を少し詳細に説明していきます。
会社への提言、新規事業計画の立案、自身のコミットメント、求められているのはすべて『持論 / 自論』
持論 / 自論とは、自分の考えや意見のことです。なぜ、今年はわざわざ、『持論 / 自論』を述べてくださいということを伝えていると…それは、自分の考えや意見を述べない、述べようとしない人が多いからです。
発表先である経営者や役員は、「その人がどう考えたか」、「なぜ、そう考えたのか」を求めているのにも関わらず、情報をまとめて発表する、選択肢を提示する、「というわけで、現状の計画のままがんばります」というケースが多く見受けられます。
そして… 『持論 / 自論』を述べてくださいと促すと結構、抵抗されます… そんなに嫌かなぁ…
AIの出現で「情報をわかりやすくまとめる」、「情報を解釈する」価値は急速に下がっている
最近、実感するのは、「情報をわかりやすくまとめる」、「情報を解釈する」価値が急速に下がっているということです。
ネットには情報が溢れていて、動画も見やすくまとまっているものが多く、コンサルタントが多くの会社に出入りしていて、人材の流動化も進んでいるために、情報自体の希少性はなくなりつつあります。
それに加えてAIの普及により、あるテーマについて「普通だったらどんなことを考えるのか」くらいであれば、極端な話、誰でも考えることができるようになりました。理解できなければ、理解できるまでAIに聞けば一通りの理解はできるでしょう。
その上で、「いま」、「ここで」、「あなた」はどう判断するのか、考えるのかに価値がある(逆に、そこにしか価値がない)というのが現在の状況です。個人的には現在のAIが持ちえない身体感覚や感情(気持ち悪い、気持ちいい、すっきりする、もやもやする、うれしい、いやな気持など)を上手に捉えられるかが人間の価値になっていくと思っていますが… これはまた、別の話ですので、また、今度。
やはり、『持論 / 自論』を話さなくてはいけなくなっているのです。
そうは言っても人前で『自論 / 持論』を述べるのは嫌だよね。気持ちはわかります
とは言っても、人前で『自論 / 持論』を述べるのに抵抗がある気持ちはよく理解できます。理由としては、以下のようなものが挙げられるでしょう
- 『自論 / 持論』と言われても… よくわからない ← 実はこういう人は多い
- あっているかわらかないことは話したくない
- 質問されても回答できるかわからない
- 自分の意見や考えが反対、批判されるは嫌だ
これはその通りだと思います。よくわかります。これは、半分は、「慣れないと仕方ないよなぁ」と思う反面、もう半分は、「周囲がもう少し配慮してあげないといけないよなぁ」と思います。
勇気を持って自分の意見や考えを述べた結果… そこから的確に議論されて、最終的に「述べてよかったなぁ」とならなければ、次からは意見を述べるのを止めようとなるでしょう。実際、そのような議論になるケースがどれくらいあるのだろうと思うと、『自論 / 持論』を述べるのを避けたくなるのも仕方ないでしょう。
『自論 / 持論』は周囲との『議論』を通じて形成される
『自論 / 持論』は『形成する』という表現を使います。様々な情報を集めて、何度も考えた上で「結果としてできあがる」ものだと理解しておくとよいと思います。
私が研修やプロジェクトでは下記のような案内をしています。
- 最初はとにかく、手に入る限りの情報を集めてください。いろいろな人の意見を読んだり見たりしてください
- それをしながら、自分なりに、よいと思うもの / そうでないもの、賛成するもの / 反対するもの 等、自分なりの感想を持っていってください
- ある程度、情報や意見が出揃ってきたら(これは、もう新しい情報や意見が出てこなくなるのでわかるはずです)、自分が考えていることを全部書き出してください
- その上で、周囲の詳しそうな人と議論をしてください。議論とは、自分の考えを伝えて、それに対する賛成、反対の意見をもらうことです。できれば、両面実施してください。その上で、相手がそれに対してどう考えるかも聞きましょう。それに対して賛成意見、反対意見も述べてください
- そこまでやって、みなさんが「本当にそうだなぁ」と思ったことが『自論 / 持論』です
大切なのは『自論 / 持論』は自分だけでは作れないということで、様々な情報や周囲との議論を通じて、ある程度時間をかけてできるものだということです。なので、『形成する』という表現をします。他の『論』が存在した上で、『自論 / 持論』は存在しますので、この点は忘れないようにしましょう。
『自論 / 持論』を述べよう!議論をしよう!見解の相違、判断の違いを楽しもう!
今年、多くの会社様でお話するのが、「最終報告 / 最終発表は必ず、議論になります。大絶賛!質問、批判なし、スタンディングオベージョンで即GO!みたいなことはあり得ません。必ず、質問や確認はあるし、様々な観点から議論することになります。そのつもりでいてください」ということです。
当たり前のことですが、『自論 / 持論』に正解はありません、人によって違います。それを持ち寄って、見解の相違や判断の違いを確認して、その上で、チーム(企業)としてどうするかを判断するのが議論の目的です。
なので、基本的には『自論 / 持論』を述べるときには、「人間が違うので、違いますよね~。みなさんはどう思われますか?なぜですか?さぁ、語り合いましょう」という気分で構いません。躊躇せずに話してしまいましょう!
本当は、議論するリテラシーにも言及したいところですが、本日はそろそろ疲れたのでこの辺で。毎回、意思決定者にお伝えしているセリフを紹介しておきます。
「これからみなさんは、『自論 / 持論』をお話します。それぞれ見解の相違はあると思いますが真剣に考えた結論なので、真剣に聞いて建設的な議論をしてください」。
なかなかそうならないからお話するのですが… そういえば、当社のコンテンツで『建設的な批判』のコンテンツがありましたので、興味のある方はこちらご覧ください
『建設的な批判』とその鍛え方
年末年始、最終発表会 / 報告会、がんばっていきましょう!
最後になりましたが、本年も株式会社アイディアポイント、日本イノベーション協会、お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願いいいたします。 <(_ _)>
本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
株式会社アイディアポイント
代表取締役社長
岩田 徹