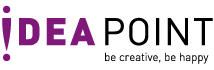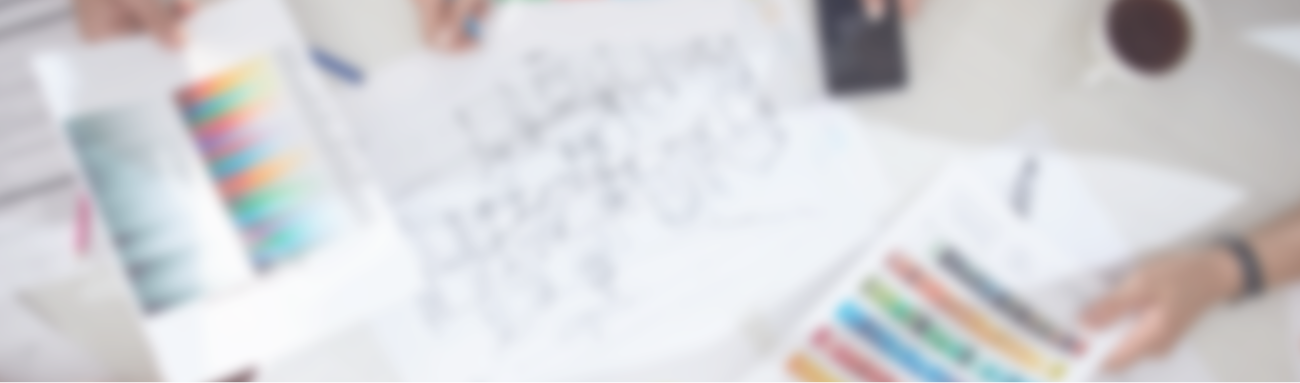アイディアポイント岩田です。私たちの会社では、年度末までの施策が一段落して、ビジネス的には4月は比較的スローな時期です。2025年4月は新しい仲間が2名、参画する予定なので、しばらくは、引き継ぎや立ち上がりの支援が業務のメインになりそうです。
4月は卒業と入学の季節ですね。新しい職場にチャレンジする人も多いのではないでしょうか。実は、私は新しい場所に入ってキャッチアップする(状況を把握して上手に入る)のが得意です。新しい会社で働きはじめる、プロジェクトに途中から入る等、よくあることですが、比較的スムーズに働ける才能があるのではないかと思っています。
今回のテーマは新しい職場やプロジェクトの中で、『スムーズに働けるようになるか』について書いていきます。
最近では、新入社員 / 中途社員が会社に参画する際に実施する各種の施策のことを『オンボーディング』という表現をします。『オンボーディング』は、人事(≒会社)が新入社員 / 中途社員がスムーズに活躍できるような環境を整えるという文脈で語られることは多いですが、個人の立場からどうすればスムーズに新しい職場やプロジェクトに入ることができるかという点で語られることは多くありません。今回は過去の経験からそのコツについて書いていきます。
『オンボーディング』とは、船や飛行機(≒会社)に乗ることだが… それ、本当?
オンボーディング(on-boarding)とは、元々は、『船や飛行機に荷物や人を乗せる / 乗る』ときに使う表現です。そのイメージを会社に重ね合わせて、上手に乗船 / 搭乗しましょうというのが基本的な考え方です。きちんと搭乗口で人が集められ、安全なタラップを順番に案内され、全員が席に着いたことを確認、安全が確認できたらハイ出発!というイメージです。
私個人は、少し違ったイメージを持っています。どちらかと言えば『走っている車に飛び乗る』くらい、もう少しソフトでも『動く歩道にタイミングよく乗っかる』、『スキー場でリフトに乗る』、『観覧車に乗車する』くらいのイメージです。
『すでに動いている』ものに『自分がタイミングを合わせて乗る』という意識を明確に持つことがポイントです。
人事の世界では、『オンボーディング』というとしっかり準備して、いろいろお膳立てして、満を持して現場へ配属という議論がされることが多いようです。もちろん、それも大事ですが、私自身は、『助走をつける』、『現場と同じ速度まで勢いをつけて飛び乗れるようにしておく』ことが重要なのではないかと感じています。
全力で『ダッシュして』乗り込む – ボーとしながら乗らない、ゆっくり乗らない
私の経験で言うと、『ひとまず、経験しながら徐々に仕事を覚えていこう』という人や職場も多いように感じます(これは本人の問題だけではなく、上司や周囲の人も口にする表現です)。このイメージは意外とよくないのではないかと思います。
自身も受け入れ側の職場も「早く馴染んでスムーズに働けるようになりたい」気持ちは同じはずです。であれば、多少大変でも最初から近しいスピードで働けるイメージを持っていた方が楽なのではないかと思います。
私の感覚では、「とりあえず、取り組みながら覚える」のでは、遅すぎます。普通の職場は、猛スピードで動いているし、後から参加する人材は早くそのスピードに慣れて同じように働けるようにならなければいけません。
「とりあえず様子を見て…」「一度、話を聞いてみてから考えて…」という余裕は本来、ないはずです。なので、『ゆっくりでいいよ』と親切に言われたとしても、それを鵜吞みにせず、まずは、自分なりに全力で『ダッシュして』乗り込むくらいの気分で取り組んだ方がよいでしょう。
私もプロジェクトの初回は、一番、気合いを入れて準備します(もちろん、他の回も気合は入っていますが)。ある情報は全部集める、考えられるあらゆる場合を想定しておく / 仮説を考えておく、これをしておかないで、「まぁ、状況もわからないし、ひとまず、話を聞いてから考えましょうか」などとしていては、いきなり出遅れる可能性があって、さらに、その出遅れは取り戻せない…ものです。
最初はわからないことが多いのでどうしてもスムーズに仕事ができませんが、慣れてしまえば、スムーズに働けるようになります。なので、多少、大変でも最初に一気に覚えた方が現実的には楽だと思います。
この後、『乗る側(=新しく入る側)』の観点からいくつかそのコツを書いておきたいと思います。
最初に教えてもらえることなんて全部は覚えられないから、とにかく、メモに残しておく。どこにあるか覚えておく
新しい職場、プロジェクトに『後から参加』した人は、最初はどうしても覚えることが多くなります。親切に教えてもらっても実際に頭に入ることは多くありません(残念ながら人の頭にはそんなに多くの情報は入りません)。これは仕方のないことです。かと言って、最初に話しを聞かないわけにはいけません。新人研修やオリエンテーション研修の内容を全部、頭に入れておくことは多分、不可能です。
まずは、できるだけ覚えましょう。覚えられないことはどこにその情報があるか覚えましょう。それも覚えていられないものはメモに残しておきましょう。最初に、基本的な知識や用語が頭に入っていないと仕事になりません。可能な限り覚える、覚えきれないものはどこにあるか覚える、それもできないものはメモにしておくのがおすすめです。
「必要になったときにまた聞けばいいや」では、いつまでたっても覚えられません。大変ですが、できる限り頭に入れつつ、メモはしっかりとっておきましょう。
情報は取捨選択せずに全部聞く。自分に関係ないことはない
「自分なりに重要なポイントを覚えるよう、理解しよう」と考える人は意外と多いようですが、新しい職場やプロジェクトではあまりおすすめしません。
「何が重要なのかは、まだ、わからない」ということがその理由です。最初に説明してもらえる内容は誰かが「これは知っておいた方がよい」と考えた内容でしょう。自分が詳しくないことは、情報の取捨選択をしないで、一旦、そのまま聞いておいた方がよいでしょう(というのが私の考えです)。
研修やオリエンテーションで「ここは自分には関係がないから」と聞き流していたところが、後になって、実は聞いておかなくてはいけなかった…という例はあちこちで多発します。研修の企画者は、『必要だと思って』その内容を入れているので、やはり、それなりの理由があるのです。
私は、自分に関係ある / なしに関わらず、どんな話にも興味があります。どんな話も一旦、そのまま、興味深く聞く能力?習慣?があるので、この点はよかったなといつも感じます。
「自分に関係のあることだけ知っていればいい」というのも正しいのですが、最初はなかなかこの判断はできないですからね。『一旦、聞く。判断は後』、上手にオンボードするコツなのではないかと思います。人はよく話を聞く人に、よく教えますからね。
最初は、多少、バランスを崩しても気にしない。流れにのること、前に進むことを優先する
動いているものに飛び乗るとバランスを崩すのは当然のことです。ところで、動く歩道に上手に乗るコツはなんでしょう?以下のようなことが言えるのではないかと思います(逆に、この辺りがうまくできないと下手なのではないかと…)
- きちんと勢いをつけて乗る
- 重心を残しながら恐る恐る乗らない
- 手すりを持ちながら乗る
- 多少、バランスを崩しても気にせずに歩く。しっかりと顔をあげて、歩きながら調整する
コツは、あまり細かいことを気にしないで足を動かして前に進むことです。動く歩道が余裕の人は、動いているランニングマシーンに飛び乗るイメージを持つとよいのではないでしょうか。ボーっと飛び乗ると転びます。
職場であれば、自分の本来の役割と責任、チームの目的・ゴールといった先のことをしっかりと見ながら(これで、頭があがり安定する)、思い切って働く。最初は、手元の仕事はとりあえず、ギリギリでもやっつけながら進めていけば慣れてきて安定して働けるようになるというところでしょうか。マニュアルや同僚、上司のサポートという補助まであれば完璧です。
既にある業務やチームに後から参加したら違和感を感じたり、ついていけないところが出てくるのが当然です。違和感はそういうものだと理解しながら、とにかく、早く慣れて、同じように働けるように意識していきましょう。
仮説を持って仕事にあたる、経験的に学ばない – 経験しないとわからないはウソ
私が意識しているのは、「経験的に学ばない」ことです。もちろん、「経験しないとわからない」、「経験からしか学べない」ことは多くあります。一方で、「経験しなくてもわかる」ことがあります(あるいは、似た経験をしていれば応用できることも多くあります)。実は、「少し考えればわかる」ことは多くあるものです。
例えば、「経営会議には必要なデータ」について。もちろん、最終的には、その会社毎に異なるので、経験してみなければわかりません。一方で、経営会議(経営の意思決定)として、必要な情報は、他社の事例や現在の経営環境を考えればある程度、予想できるはずです。
仮説思考という言葉にはなりますが、取り組む前に、「予想する」、「自分なりに考えてみる」、「その準備をする」経験をして、それとの比較をしながら学ぶことが重要です。
「確実にできること / 絶対にできること」を積み重ねていく。ざっくり理解して何もできないを避ける
これは、最初の会社で先輩に言われたことです。『岩田君、なんとなく理解できていて全部あやふやなら、少なくても「これならできる」ものがいくつかあった方がありがたいよ』。本当、すみません。何もできていませんでした。
どうしても最初は、全部、一気にできようと考えてしまいがちですが、それでは、なかなか周囲の役に立てません。実は、一つずつ確実にできることを増やしていった方が、周囲に貢献できるものです。範囲の広いプロジェクトに取り組むときには、つい、「全部、理解して、すぐにできるようになりたい」と考えがちですが、それよりは、「確実にできる」ことを積み重ねていく方が周囲の役に立てるでしょう。
大事なことなのでもう一度。徐々にペースを上げながら慣れるはウソ。助走をつけて飛び乗るべし!
今回は、『オンボーディング』について、個人として意識することをまとめてみました。このテーマは、もう少し深く考えて、具体的な事例とワークを用意すれば研修コンテンツになるかもしれない… と思いました。
どんなことでもそうですが、意外と『最初』の印象は大切です。自身にとっても、最初に評価を得られればその後、落ち着いて仕事に取り組むことができるでしょう。最初に周囲の評価を得られれば、自分の気持ちとしても余裕が出てくるでしょう。その後、多少、うまくいかなくても周囲から猶予が与えられます。
実は、仕事の質、スピードは、慣れてしまえばそれほど大変ではなくなります(どんなことも当たり前になってしまえば、なんてことはありません)。場合によっては慣れてきたらある程度、スピードを落とすことも可能です(スピードは上げるのは大変ですが、下げるのは比較的容易です)。これらの観点から見てもやはり、最初はのんびりとせずに、スタートダッシュするのが得策でしょう。
4月に新しい環境で新しいチャレンジをスタートする方も多いのではないでしょうか。新しいことにチャレンジするのは大変ですが、楽しみですね。みなさんもオンボーディング、のんびりせずに、助走をつけて思いっきり飛び乗っていきましょう。
本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
株式会社アイディアポイント
代表取締役社長
岩田 徹