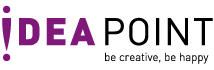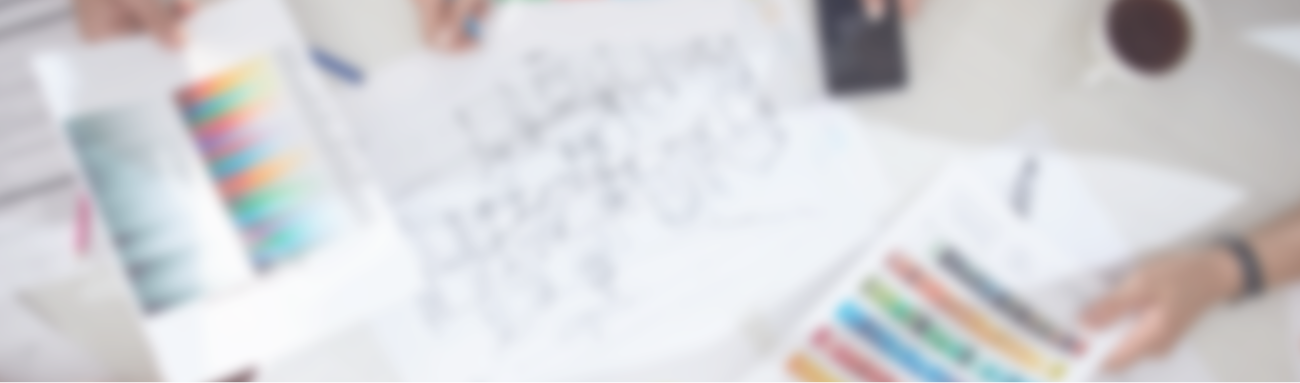アイディアポイント岩田です。祝100本目!!ということで気がついたら社長ブログ、今回で100本目でした。小さいころから「お前は落ち着きがない、飽きっぽい」と言われて育った身としてはよく100回も文章書いたなと自分をほめたいと思います。継続は力だと信じる今日この頃です。
さて、7月に入って急に暑くなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。7月は比較的スローな時期なので、お世話になった人に会いにいったり、外に出て議論したり、新規の営業などをしています。同時に、最近はシーズンなのか営業電話も多く受けることがあり、可能な範囲でいろいろな人と会うようにしています。
今回は、オンライン会議が一般的になったいま、あらためて、最近、『いまさら感じる』オンライン会議、面談の難しさについて書いていこうと思います。こういうことも早晩、スキル化されてオンライン会議上手な素敵なビジネスパーソンだらけになるのかなぁ、いやいや、もっとデータ活用が進んでジャストタイミングのときにしか会議、面談しなくなるのかな、いやいや自動電話みたいに相手もAIになってくるのかなどなど妄想してみたりしますが、今回は、地に足をつけて、『目の前』でどうするのかについて書いていきます。
※:今回は人間である岩田とChatGPTの合作です。岩田がカルピスの原液で、それを飲みやすい濃さ(薄さ?)にしてくれるChatGPTさんのイメージです。
『初対面』こそ対面で話す必要があるのに、初対面が一番、オンラインになりがち問題
コロナ禍以降、私たちの働き方やコミュニケーションのスタイルは大きく変わりました。中でも、オンライン会議はすっかり日常の一部として定着しました。今では多くの人が使い慣れていて、マイクがつながらない、映像が出ないといったトラブルもほとんど見かけなくなりました。
その便利さゆえに、「会わなくても話せる」ことが当たり前になり、さまざまな場面でオンラインが活用されています。ちょっとした確認や意見交換であれば、わざわざ出かけずに済むオンラインの方が効率的です。すでに顔見知りの相手なら、わざわざ会わずとも、信頼関係をもとにスムーズに話が進みます。
しかし、最近、私が特に気になっているのが「初対面のやりとりこそ、なぜかオンラインになりがち」ということです。本来、初めて会う人とは、できれば直接顔を合わせて話した方が、お互いの雰囲気も伝わりやすく、細かなやりとりもしやすいものです。声のトーンやちょっとした表情、相手のしぐさなど、画面越しでは感じ取りづらいことが、対面なら自然に伝わってきます。聞き手にとっても、「この人はどんな人なんだろう?」といった人となりがわかりやすく、信頼関係を築く第一歩としては大きな意味があります。
一方で、「わざわざ会うほどの話じゃないかも…」という迷いもあるのが現実です。特に、商談のような場では、「お互いの時間を効率的に使いたいから、まずはオンラインで」という選択をすることも少なくありません。その判断自体は合理的ですし、忙しい現代においては理解できます。
ただ、私自身の経験として、新規のアポイントや初対面の相手との会話が、オンラインだとうまくいかないことがよくあります。話が盛り上がらなかったり、相手の反応が読みにくかったりして、結果的にお互いの理解が浅いまま終わってしまうことがあるのです。「やっぱり直接会っていたら、もっと自然に話せたのに…」と感じる場面が何度もありました。
だからこそ、あえて今、「初対面こそ対面で話す価値がある」ということを見直してみたいと思っています。もちろん、すべてのやりとりを対面に戻す必要はありません。でも、信頼を築くうえで大切な最初の一歩だけは、少し面倒でも直接会って話すことが、お互いにとって良い結果を生むのではないでしょうか。
私から見た初回のオンライン面談が上手な人の共通点– オンラインでは「なんとなく」は伝わらない。にっこり、はっきり、くっきり話すべし
複数の企業から営業を受けてオンライン面談が上手な人の共通点をいくつか洗い出しました。書いてあることは当たり前のことばかりですが、なかなかよいリストになっていると思います。
- 対面で話すときよりも、明るく、はきはきとわかりやすく話します。声のトーンも少し高めで、聞き取りやすさを意識しています
- 相手が話し始めるのを待つのではなく、自分から会話をスタートさせます。その方がスムーズに場が動きます
- 話し始める前に、「今日はこういう流れで話します」といったように、最初にきちんと話の構成を説明します。
- 一つの話題について話す時間は長くても5分以内におさめます。だらだら話さず、ポイントを絞って伝えます
- 表情は笑顔で、身振り手振りも大きめです。少し落ち着きがないように見えることもありますが、それが逆にエネルギーを感じさせます
- 相手の理解を確認するために、「ここまで大丈夫ですか?」などと細かく確認してくれます
- 会議や面談の前に、相手のことや話す内容についてしっかり調べて準備しています。そのため話にムダがありません
- 話が終わるときは、「今日はこれが結論です」などと、しっかりとまとめて締めくくります。
- 打ち合わせが終わった後は、すぐにお礼の連絡や資料の送付など、フォローが入ります。気配りができるところも魅力です
ポイントは、これらを「わかりやすすぎるくらいわかりやすく」実践することです。オンラインでは、「なんとなく」では伝わりません。こういう当たり前のことを1.5倍くらいきちんとやることが好感度を上げるのに役に立つではないかと思います。
逆に、オンラインになると「ここは気になる」ポイントも結構、多い – 特に、音声、身振り、手振りは要注意
個人的には、オンラインは、「こうするべき」よりも「こうしない方がよい(NG行為)」の方が多いと感じています。特に、音(声)に関しては、自分自身で確認することがなかなかできない(相手の環境に依存していることも多い)ので、注意が必要だと感じています。下記に、私の中で気になったものを挙げていきます。
- まず何よりも「声」が大事です。イケメンボイスかどうかではなく、落ち着いていて聞き取りやすい声が一番印象に残ります
- まわりの雑音が入ってしまうと、聞き取りにくくて印象が悪くなります。たとえ仕方のない環境だとしても、うまくミュートを使うなど、相手が聞きやすいように配慮してほしいです
- ネット環境やツールも使えなさすぎると「スムーズでない」ので気になるケースは多いです
- 画面が小さいので見た目や服装は、正直あまり気になりません。よほど変な格好でなければ、清潔感があれば十分です
- 顔や髪をしょっちゅう触るしぐさは、意外と気になります。落ち着かない印象を与えてしまうので、あまりやりすぎないように意識しておくとよいです
- 自分から話そうとしない人や、返事のタイミングが遅い人は、オンラインでは特に目立ちます。少しくらい相手の話とかぶっても大丈夫なので、積極的に話す姿勢を見せることが大切です
- ひとりでずっと話し続けるのは、5分でも長く感じることがあります。話すときは10分以内を目安にして、途中で「ここまででご質問ありますか?」などと、相手の様子を確認しながら進めると好印象です
オンラインでは、よくも悪くも「映っているものがすべて」です。ほぼ挽回はできないと言ってもよいでしょう。その限定され中で、ミスなくきちんとやらないと「どんどん減点されていく」ものだと理解するべきだと考えています。
私たちは、今後、オンライン時代の『初対面』、『新規開拓』にどう取り組むか – 結論はないけどいくつかの方向性
オンラインでの「初対面」が難しいのは、ある意味仕方のないことです。まずはそれを受け入れるところがスタートです。そのうえで、「にっこり」「はっきり」「くっきり」を意識して、少しずつスキルを身につけていくことが大切です。また、NG行動を知って、きちんと練習しておくことも重要です。ここは本当に重要です。自分としては嫌でも動画を録画して、それを見直すようなことを何度もしなくてはいけませんね。
次は、オンラインで初めて会う前の「準備」、「会い方」を戦略的に考えることが必要です。いきなり「はじめまして」や「とりあえず会ってみる」はできるだけ避けて、少しでもお互いに安心感や信頼感を持てるような形にもっていくことがポイントです。できれば、会う前から「この人となら話せそうだな」と感じてもらえる状況にもっていく作戦を考えていかないといけません。
そのためには、既に関わりのあるお客さまやパートナー、知人から紹介してもらったり、あらかじめ私たちのことを知ったうえで会ってくれる人を増やしたりすることが効果的です。一言で表現すれば「マーケティングの強化」ですが、単なる数字や戦略ではなく、人と人が共感し合えるようなつながりを意識することが大切です。共感、興味関心です
「会うタイミング」の設計もとても重要です。今後は、企業同士の取引(BtoB)でもデータを活用したマーケティングがどんどん進んでいくでしょう。でも、私たちには使える時間や人の数など限界があります。だからこそ、何をどうするかをしっかり考える必要があります。ここはしばらく回答がでなさそう…です。有識者のみなさん、ぜひ、議論させてください。
最終的な理想は、『ストーン・スープ』です。「あの人たち、なんだかおもしろそうなことをしてるぞ」と自然に人が集まってくる。そんな魅力的なチームや場所をつくっていくことが、私たちのゴールです。
(参考:「ストーン・スープ」の話:https://ideapoint.co.jp/blog/ceoblog023/)
ということで、今回は、オンラインにおける「初回面談」の難しさとその攻略法をテーマに書いてみました。まだまだ結論には至っていませんが、今後、ビジネスを進める中で必ず問題になるテーマになるでしょう。ということで、しばらく、頭を使い続けてみようと思います。
本記事に関するご質問やコメント、疑問に感じた点がございましたら、ぜひ、お問い合わせフォームより連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。
株式会社アイディアポイント
代表取締役社長
岩田 徹